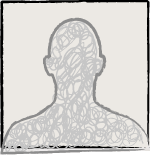|
感情表現という修行
役者とは、いわば、自らの身体のすべてを駆使して、感情表現をするプロのことだと言えよう。その際、表現されるべき「感情」とは、もちろん劇中人物、つまり他人の「感情」だ。だが、その「感情」にリアリティーを持たせ、見るものの共感を呼ぶためには、自分自身の内側から、真実の感情をひとかけらなりとも探し出し、それによってただの台詞を生きたことばとしなければならない。その作業が容易ならざることは、映画が進むにつれて明らかになってゆく。
学生たちだけではない。稽古場では指導官も自分を剥き出しにしてくる。それがどんなに些細なシーンであろうと、指導官は手を抜かない。納得するまで何度もやり直させ、時には双方攻撃的になって、とんでもない言葉が投げ交わされる。一学年30人足らず、という濃密な人間関係に加えて、学期末の試験はすべて三回までしか受験する事が許されない、という厳しい条件に、途中で辞めてしまう学生は跡を立たない。
虚構と現実のあいだで
批判が身にこたえるのは、それが多くの場合、意図的に演技者自身の感情を掻き立てることを目的としているからだ。指導官たちは容赦しない。彼らが自分を超えて、感情そのものを体現するに至るまで、執拗に挑発しつづける。虚偽である感情をいかに真のものとするか、素の自分からいかに離れる事が出来るか、そこに演技のすべてが掛っているかとでも言うように。
虚構と現実の間の往還――しかもそれは、夢とうつつのあわいをたゆたう、などといった穏やかなものではなく、両方の世界のきしみを背負わされ、そのはざまをいきつづけなければならない役者という特殊な生き方が強いる、自分自身との対決といえるほどに激しいものだ。
「私」の破れる瞬間
メディアの中には、本作撮影中に発表された問題作、ドイツ赤軍の青年がドイツ銀行の頭取を殺害した事件を扱った『ブラック・ボックス・BRD』も記憶に新しい監督アンドレス・フェイエルが、今回なぜ「役者」という全く違う素材を選んだのか、という疑問を抱いたものも少なくない。だが、彼の関心は、ここでも一貫している。彼自身のことばを借りれば、彼の視線は常に「危機的な状況におけるセルフコントロールの喪失」の瞬間にむけられている。言い換えれば、それは、「私」という自己像、すなわちアイデンティティーが揺るがされる瞬間だ。
実際、この映画を観ることは、日常ではなかなか出会うことのない、あるいは出会うことを無意識のうちに避けている、個人の感情の強い自己表出に出会うことを意味する。それゆえ、この映画はある意味でひどく「重い」。
ここでは、粉砂糖をまぶせられた余所行きの感情が、装いを凝らして供されるのではなく、喜びにせよ、怒りにせよ、未加工の想いが張り切った強度のままに突然投げ出される。ハンドカメラを駆使した映像は、時には、息遣いまでとらえるのかと思うほど、人物のそば近くまで接近する。「映画」と言うにはあまりにも生々しいそれは、観る人によっては一種のショック体験ですらあるかもしれない。ときに獰猛な野獣のようにあらわれ、「私」という枠を突き破ってしまう感情というもののパワー、それは、私たち観るもの自己意識をも揺るがさずにはいない。なぜなら、そこには生のひとつひとつが抱える条件が、裸形のまま確実に反響(こだま)しているからだ。
恐らく、フェイエルは、そのような瞬間をより鮮明にとらえるために、今回「役者」と言う素材を再び選んだに違いない。再び、というのは、実はフェイエルは、『ブラック・ボックス』のような困難な社会的・政治的なテーマに意欲的に取り組む一方、デビュー当初から「役者」というテーマにも変わらぬ強い関心を示しつづけてきたからだ。「役者」という生き方に、どうやらこの作家は、凝縮した生の雛型を見出しているのかもしれない。
* * *
ドキュメンタリー作家として、既に高い評価をほしいままにしているフェイエルだが、近年では演劇にも関わり、次回作にはゲルト・コーエン原作のテロリストを主題にしたフィクションの映画化を準備しているという。素材と形式に極めて意識的なこの作家が、テロリズムという、ドイツ国家にとっての「苦い過去」を、今度は虚構という形を借りてどのように見せてくれるのか、楽しみなところである。
]『壁に向かって』 Gegen die Wand(独 2004年)
『兵士と女王』 Der Krieger und die Kaiserin
『泣く駱駝の物語』 Die Geschichte vom weinenden Kamel
|