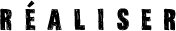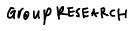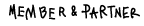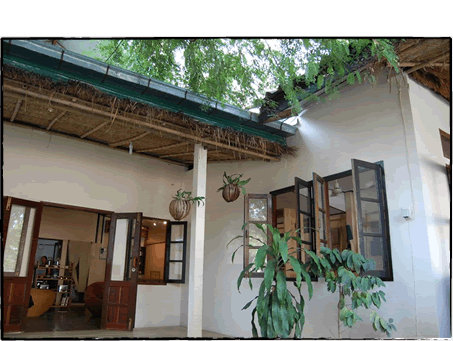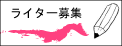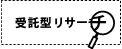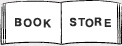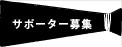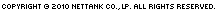|
 |
ビエンチャンの名前のないカフェ
|
|
|
|
 |
| 2010-02-28 |
|
|
|
| |
|
アラビカ・ティピカとの出会い
メコン川沿いの賑やかなファーグム通りから少し入ったところにある、名前のない小さなカフェ。店先には「house roasted coffee」の看板が掲げられ、そこがカフェだと気付かないで通り過ぎてしまいそうな小さなお店。この店の店主、松島陽子さんにお話を伺ってみた。
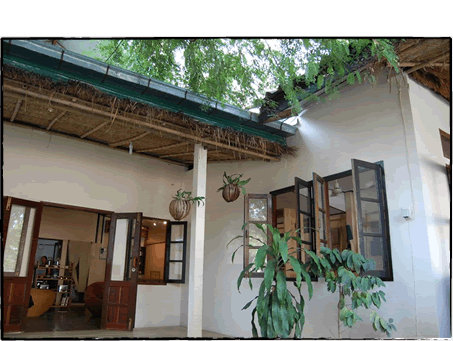 
大学院で農業経済学を学んだ松島さんは、ラオスのコーヒーを研究対象にし、何度もラオスの生産農家のもとを訪れ、コーヒーを研究する日々が続いていた。そこで出会ったのが「アラビカ・ティピカ」だった。
この豆はアラビカ種の一つで、ラオスにおいては生産量が少ないのだが、森の奥でも育てることができ、あまり手をかけなくてもよい(というより、手をかけるには地理的に困難な場所で育っている)品種で、そこがちょっと「ラオスらしい豆だな」と、感じたという。それに、味見をしたら、「美味しかった」というのも、この豆にひかれた理由の一つだった。
研究で足しげく農園に通ううちに、農家から「なぜあなたは、豆を見に来てばかりで、買わないのか?」と、聞かれたという。豆の買い付けに来ていると思われていたらしい。
彼女を魅了したアラビカ・ティピカは、「買い付けて輸出するほどの生産量はないものの、ラオス国内で売る分には、十分」な品種であり、「このおいしい豆をぜひ、多くの人に知ってもらいたい。このままでは、ともすれば消えてしまうかもしれない」と思い始めていたところ、当時お手伝いをしていたお店の一角でコーヒー豆を売ってみないかという話が持ち上がった。
結局その話は頓挫してしまったのだが、「それなら自分でお店を」と、2004年から一年半かけて、店の準備を整え、2006年11月、現在のカフェがオープンした。
コーヒー生産農家とのつながり
コーヒー豆の買い付けは、基本的には年に一回だけとのこと。今年で3年目なので、まだ買付の回数も3回ほど。コーヒーや茶の産地として有名なパクソーンに足を延ばし、農家に出向いて、直接顔を合わせ、豆を買い付ける。農家の手で果肉を除去した、パーチメントと呼ばれる状態の豆を仲買人の家庭に運び、そこでいったん保存してもらい、必要に応じて脱穀してビエンチャンの店に運んで、そこで選別、焙煎をして店に出している。このパーチメントの状態で買い取るのが、農家にとっても松島さんにとっても、都合がよいという。農家にとっては手間が省けるし、松島さんにとっては、品質管理が容易になる。
「これまで大変だったことは?」の問いに、松島さんは少し考えて、「天候に豆の出来が左右されることと、産地の状況がリアルタイムでつかめないこと、そして、農家とのやりとりですね。農家とは直接会って話す以外、交渉しようがないですから」と。彼女は、仲買人のお宅に泊まり、生産農家と交渉することもあるという。
ラオス語で交渉するのに苦労はないですかと聞くと、「大体、決まったことしか話しませんから」大丈夫とのこと。ただ、彼女の物静かな話しぶりからは、日々の苦労を感じさせない落ち着いた空気が感じられた。「従業員が定着しないのも悩みでしたが、スタッフを四人に増やしてからは、辞めていくこともなくなり安定しています」と話された。
 
カフェのこれから
松島さん曰く「コーヒービジネスは儲かりません」。それでも彼女がカフェを続けて行くのは、「ラオスで自分にも何かできそうな気がするから」。ラオスの事情にも詳しくなり、産地とのつながりもできた。これからは、豆の量を増やし、産地との関係をさらに深めて、「あとはお店をつぶさないようにしたいですね」とのこと。
仲買人さんとは、家族同様の付き合いだそうだが、農家とはまだまだこれから深めていく余地があるという。「カフェをやっていて良かったと感じるときはどんなときですか?」とたずねると、「毎日自分で淹れたコーヒーを飲むときに、生産農家をはじめ、関わるすべての人の顔を思い浮かべることができるときですね」という。
最後に「なぜお店の名前がないのですか?」と質問すると、「実は、ラオス人の作家に名前を頼んだのですが、ちょっとピンとこない名前だったので・・。頼んだ手前、他の名前をつけるわけにはいかないですし。今後、これだと思える名前にめぐり合えば、それに決めるかもしれないです」ということだった。
彼女の店については、町の情報紙などで見かけることがほとんどない。それに関してたずねると、「店の前を通って、『あ、なんだか惹かれるな、入ってみようかな』と感じてくれる人にだけ、来てもらいたいんです。お客さんを選びたいんです」と彼女は話す。確かに彼女の店は派手な音楽もなく、装飾も控えめで、いちどきに大人数の客が入ることも少ない。だからこそ、いつ来ても、ゆっくりした時間を約束されているのだ。店の周りは、ほどよく木立が繁り、南国の日差しをさえぎってくれて、とてもさわやかだ。
帰り際、豆を買った。「この豆は誰がどこで、いつ焙煎しているのです?」ときくと、店の裏を指し「ここで、スタッフたちと、毎日焙煎しています」とのこと。
焙煎したての豆を、帰ってからさっそくいただいたのだが、酸味控えめで、口当たりがやさしく、松島さんが魅了されたのも納得の味だった。
義手・義足支援NGO『COPE』をたずねて/ラオスと不発弾
ラオスのオーガニック市場をリードする『XAO BAN』という会社
|