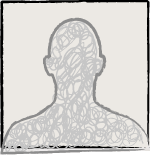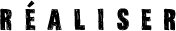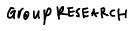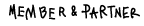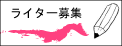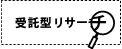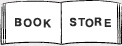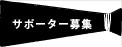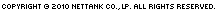|
『ローラ』では赤毛のパンク少女というパワフルな少女を演じたフランカ・ポテンテだが、本作では患者から愛される金髪の内気な看護婦シシィを演じている。聞き取られることを拒んでいるかのような控えめな話し方から、今にも転びそうなたどたどしい歩き方まで、走ってばかりいたパワーガール「ローラ」のイメージを持って映画を観始めたものにとっては、目を見張る変身振りだ。
悲しみにしろ、喜びにしろ、シシィにおいては、手放しで表現されることは決してないが、瞳の蔭りや、口元のかすかな緩みといった些細な表情によって満干の感情を伝えて余すところがない。さらに、全編に渡って寄り添うように挿入される彼女の独白、その甘やかなハスキーヴォイスは、ほとんど音楽的な心地よさを聞くものに与える。
それら俳優たちの感情表現を、丁寧に拾い上げ見事な映像表現にまで高めているのは、ティクヴァ作品のレギュラーカメラマン、フランク・グリーベ。テクノ主体の「ローラ」とはうって変わった、シンプルなピアノ曲中心の音楽は、監督自らが担当する。視覚、聴覚ともに満足できるこの『兵士と女王』は、映画ならではの感覚的な楽しさをも存分に味わわせてくれる。
狂人と常人
台詞のあちこちに「外」という語が、さまざまなニュアンスを帯びて差し挟まれ、「外側のどこかに愛が待っている」と副題に謳うこの作品は、明らかに「内部からの脱出」を主題とし、それに相応しく「精神病院」という閉じた世界を主な舞台としている。 同様の設定の物語では、医者と患者のどちらが本当に狂っているのか、というテーマがよく見られるが、ここではしかし、「正常」「異常」の境界は、さほど曖昧にされているわけではない。
患者とスタッフは、確かに「こちら側」と「あちら側」にとりあえずは分別されているのだが、むしろ、「病院」という一個の閉じた世界の中で、一方が他方のポジになりネガになる、という役割分担が自然に形成されていて、そこから出るのは容易ではない。シシィもまた、患者の妄想に応じて、そのパートナー役を進んで演じている――あるいは惰性で演じている――かにみえる。シュタイニーに対しては「憧れの美少女」を、オットーに対しては、「優しい姉」を、という風に。
だが、この妄想の共同体は、シシィが「外側」への意志を明らかにした途端、あっけなく崩れ去る脆いものだ。そしてまさにその瞬間に呼応するかのように、シシィ自身狂人の血を引いているというショッキングな事実が明らかにされる。だが、「あんたは狂ってる」というボドの言葉に、微笑みすら浮かべながら「もちろんよ」と応えるシシィは、その事実を単なる事実の一つとして淡々と受け入れている。あたかもそれが、例えば空が青いということと何ら変わりがない、とでも言うように。
たしかに、この作品では「狂気」それ自身は、主要テーマではない。だが、狂気と正気の境目の曖昧さ、それを大袈裟に取りざたすることなくあっさりと示すその姿勢は、かえって世界に対する人間的な――つまり限界のある――優しさを感じさせてくれる。狂気はここでは排除すべき異物ではなく、我々が共有している不完全な世界の一部であり、また一人一人の人間の一部なのである。
手紙と言うメディア
ティクヴァ作品のもう一つの楽しみは、個々のメディア対するその注意深い眼差しである。古典的とも言える単純な設定を、三つの異なるストーリーとして描き、それ自体「物語」に対する批評的な作品として高い評価を受けた前作『ローラ』でも、「電話」というコミュニケーションツールが重要な役割を担っていた。ここではその役割は「手紙」というさらにクラシカルなメディアによって果たされる。
映画を、そして物語を始動させることになる一通の手紙、シシィの女友達、海を見下ろす丘の家に暮らすマイケからの手紙は、シシィがボドたちのいる銀行へと向かうきっかけとなるものであり、その意味で内容的にも重要だが、それ以上に見逃せないのは、それがもたらす象徴的な意味での「外部」である。シシィがあこがれながらも、いまやほとんど省みる事のなくなった「外」の世界が、「手紙」という形をとって、閉ざされた彼女の世界――それは「病院」という内側であると同時に、彼女の「内面」という内側でもある――にかすかにではあるが風穴を穿ち、そこから「現実」をもたらすのである。
しかも、その「現実」は、「外」から一方的におしつけられるのではなしに、あくまでも彼女自身の中にわずかにではあれ生き続けている、いわば「希望」と呼応しあうことではじめて形成される。手紙がシシィに届けられるまでをスピーディーに描いた冒頭シーンは、このことをさりげなく示唆している。つまり、ここで「現実」はあくまでも、「外」と「内」の共振によってはじめて成立するのだ。そして、これこそが恐らく、この映画全体を貫くもっとも本質的なメッセージである。
希望への信頼
最終的にシシィとボドは「脱出」に成功する。とはいえ、脱出のその先に、実際に「外」があるわけではない。内側を一歩出れば、そこはまた別の「内側」なのだ。だが、違っているのは、そのあらたな「内側」にあって、物語の書き手が、いまではかれらの「過去」でもなく、患者たちの妄想でもなく、紛れもない彼ら自身であるということだ。
ラストシーンでマイケの家に到着した二人の向こうには、海が広大な広がりを見せている。「外」へそして「生」へ――雰囲気的にも内容的にもおよそ明るいとは言いがたい作品だが、それが伝える希望には、確かに深い底力がある。


]『壁に向かって』 Gegen die Wand(独 2004年)
『演劇中毒』 Die Spielwutigen
『泣く駱駝の物語』 Die Geschichte vom weinenden Kamel
|