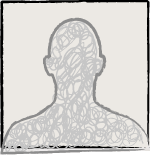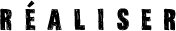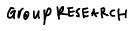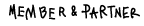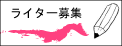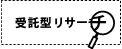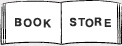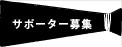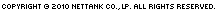[1970年代後半には5万羽いた鶏も今は1万羽あまりに減った]
1968年に開園し1984年には閉園した「仲良し幼稚園」の跡地には、当時親しまれていた都電の車輌がぽつんと置き去りにされていた。側面には、「理想郷行 あたらしきむら仲よし号」と書かれている。かつては村内でピアノ教室も開かれていたとも聞いた。かつてはそれだけ子供が多かったのだ。
空家も幼稚園の閉館も、全ては会員の減少が原因だ。現在の村に、子供は1人もいない。
その主なる理由は、
「一般に本を読む人が減り、武者小路実篤という作家すらも知らない世代が増えたからだ。」
と、村外会員の1人は指摘する。
しかし、それにしても不思議なことがある。村で育った子供たちの中で、成人して後に村に帰った例がないのだ。
現在9人いる女性村内会員の1人に、河内洋子さん(69)がいる。24才の時に入村し、以来45年間村で生活し、この間に結婚し子供1人をここで育てた。59才の時に、ギリシャで開催されている「スパルタスロン」という大会に初挑戦し、250kmを36時間以内で完走することに成功し、今でもマラソンを趣味に、野菜作りや床屋さんなどの仕事をしながら村での生活を楽しんでいる河内さんは言う。
「若い人がいなくても別にそれはそれでいいと思ってるわよ。誰かが『職がないので入ってきた』なんて言われたら、もっとさみしいもの。成人した自分の子供2人も村にはいないけど、全然さみしくないわよ。それぞれ自分の世界で活躍していて、それを聞くのが楽しいくらい。」
過疎化傾向は、「新しき村」に限らず日本の農村全体に共通している。しかし、気になるのは、この村の場合はその傾向が際立っていることだ。その理由は、ここが封建的な昔ながらの村ではなく、86年の歴史はあっても「個」を尊重する「新しき村」であることの結果かもしれない。
当然のことながら、広く入会を呼びかけることもなく、知名度アップの活動も、さほど積極的には行ってはいない。かろうじて4年前にホームページが開設されたが、それも村としてではなく会員が個人的に作成したものに過ぎない。
例年9月中旬の日曜には村祭りが開催され、村外会員をはじめ、周辺地域から訪問者が集まって賑わう。今年は、去る9月19日に行われ、たまたま来訪していた元村外会員の家族に話を聞いた。かつて実篤と共に村の創設に尽力し、13年前に亡くなったある村外会員のご子息の妻と、その息子さんだ。
「義父がこの村の会員で、そこまで熱心だったことを、私たちは生存中はまったく知らなかったんです。ムシャ先生の本は隅々まで読んでいたのは知っていましたけど、周りの誰にも会員になることも村にも誘うこともありませんでした。だから、知った時は驚きましたよ。」
以来、この女性は3回くらい村を訪ねというが、息子さんを連れ立って訪ねたのは今回が初めてだという。陶芸の修行をしているという20代のこの息子さんは言った。
「おじいさんが死んだ後、本も読んだりして、『へぇー、そうだったんだ』って少しは興味持ってましたよ。で、村に窯があるって聞いて、ちょっと見たくなって来たんです。」
他の村外会員も、一様にして「家族や友人を誘ったことなどない」と言う。
かつて実篤が生存していた時には、実篤の著書があり、自然と村の存在や活動などが外部に伝わり、それを知って希望者が集まったのだ。意図せずして、広報が機能していたと言っていいだろう。
模索する理想郷行「あたらしきむら仲よし号」
では、村全体が過疎化している村の現状を、それでよし、としているのだろうか? 村がこのまま超高齢化し、過疎化の一途をたどったならば、終いには村に1人も村人がいなくなり、ひいては村も無くなってしまいかねないのではないか?
いつの時代も、誰にとっても、理想郷はあって欲しい存在だ。こんな時代だからこそ、余計に多くの人があって欲しいと願うのではないだろうか? 私が三年前に感じた温もりは、そんな想いからだったのかもしれない。しかし、理想郷の実現もそれを維持するも並大抵のことではないのだ。だからこそ「理想」なのかもしれないが……。

[村外会員が運営する白雲荘 休日には5冊100円でリサイクル本が売られている]