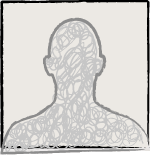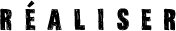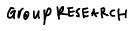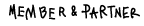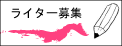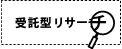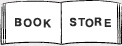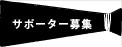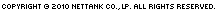|
西欧からの文化が、ものすごい勢いで日本に流れ込んだのが、今から130年以上前の開国の頃。それからと言うもの日本は、西欧から技術や政治体制をコピーすることに専念してきた。西欧の近代文化はお手本であり「オリジナル」だった。さらに、取り入れたものは「オリジナルのコピー」という枠を超え、「オリジナルそのもの」と錯覚される。 取り入れたときに、たまたまその形であったに過ぎないのに、「形」の方が、「オリジナル=本質」となってしまう。そんなおかしな例は、今日の日常生活にもまだまだ溢れていて、ちょっとした好奇心から発見することができるものだ。
つい先日の出来事。あるスペイン人の友人から「今うちにポルトガルの友達が居候してるんだけど、今日彼がご飯つくるの。食べにこない?」という電話のお誘いがあった。何でも「鱈」を使った料理だというので、普段魚に飢えている私は二つ返事で、自転車を飛ばして彼女の家に向かった。
さて、出てきた食事はというと、友達が皿に乗せてくれたマッシュ・ポテト。マッシュ・ポテトの中には、例の「鱈」がいるはずなのである。初対面のポルトガルからのお知り合いに、「で、これのどこに鱈が?」なんて質問できなかった私は、まじまじと潰されたポテトの山を、フォークでつつきながら眺めていた。「鱈はね、ほらつぶれて入ってるのよ。食べてみて。」確かにほんのり塩辛い中に、ブツッとしたものが入っている。なるほど、つまり日本でいう「干しタラ」だった。
「ババリア!」
おいしいワインと、おいしいその郷土料理を食べながら、私は英語もママ成らぬポルトガルからの訪ね人に、昔から疑問に思っていたことを思い切って尋ねてみた。「あのね、日本には16世紀にポルトガル人がたくさん来てたんだけどね。」「そうさ、ポルトガル人は、早い時期にアジアの方にまで足をのばしていたんだよ。」と自慢げに彼は声を張り上げる。その場に居たもう一人のスペイン人は「君ら、ババリアだろ。ババリア(野蛮人)。」と大声で笑って答える。
私も図に乗って、「そうそう、スペイン人も来ていてね、あんた達両方とも、日本では南の野蛮人って呼ばれていたのよ。鉄砲持ってきたりしてね。」と話すと、皆声をそろえて大笑いになる。こういう南ヨーロッパ人の反道徳的な笑いは、やはり白人世界でも一等でないという自己認識があるから成り立つのかもしれない。ドイツ人が他国の人に野蛮人なんていったら政治問題にまで発展してしまうところだが。
「で、本題なんだけど。カステラってのが日本に入って来て、今でも長崎という町では伝統的でありながら、モダンなお菓子というウリになってるのよ。」「ふーん」「でね、ポルトガルにもカステラってあるの?」「そりゃ、あるよ。」「で、どんなの?」
日本に入っている、いかにも「異国からのもの」というのは、思想にしろ食べ物にしろ、いつも胡散臭くて怪しいものだ。だから、所謂輸入元に「オリジナル」は何かと尋ねれば、意外な答えが返ってくることがしばしばある。面白いことに、そのポルトガル人の彼にとって、カステラというお菓子には、丸や四角といった決まった焼き型がなく、卵が一杯入ったふわふわのスポンジケーキ全般を指すのだそうだ。
しかもなんと、「ソースをかけて食べる。」というのである。「え!ソース??」はっきりとソースの作り方をおぼえていなかった彼は、ちゃんとした説明を与えてはくれなかったのだが、「黄色」で「シナモン」が入っているという。それはつまり「シナモン入りカスタードソース」みたいなものだろうか。彼には故郷のママに電話して聞いてもらうよう課題を与えてある。
カステラの起源
さて、その彼からの返事を待つことに痺れを切らしたせっかちな私は、カステラの起源について自分で調べて見ることになった。カステラには色々説があって、先ずはスペインにあるビスコッチョがその起源であるという説。イベリア半島中央部の高原地帯のカスティーリャ地方、そう歴史教科書でも習った15世紀末の「カスティーリャ王国」から名前を取ったというのだ。ビスコッチョ自体は、紀元前3世紀のローマ帝国支配下に既にできているという説もあるから驚き。現在ビスコッチョというと、マドリッド出身の友達によれば、薄いスポンジ状のケーキだそうだ。
もう一つはポルトガル説。ポルトガルにあるパン・デ・ローというお菓子がカステラの起源だとか。ちなみに信じがたいことに、そのローという単語は、中国の絹織物である「絽」のポルトガル綴りから来ており、まるで絽のように、ふわふわと滑らかであるところから来たという話(ほんまかいな)。
このパン・デ・ローは、北ポルトガルが発祥地で、スペインのビスコッチョ同様、16、17世紀では卵が貴重だったこともあり、貴族やお金持ちの食べ物だった。そして一般市民にはクリスマスや結婚式といった特別の日にのみ振舞われたそうだ。しかも修道院でよく作られていたとか。敬虔なキリスト教徒はよくこういう美味しい物をこっそり作っていることが多い。ドイツのビールもしかりである。
さらに調べてみると、ポルトガルのパン・デ・ローの形は18世紀には丸いものが主流になったとか。地方色が食べ物にも強く出るポルトガルでは、場所によって、日本でお馴染みの四角く切ったものもある様子。ここでは「カステラ」の語源は、白身と黄身を分けてあわ立てるときの「城のように高くなれ。」という掛け声からやってきたとか。これはスペインの友人も語っていたなあ。城というのは、その四角い形ではなくて、彼らの言語連想としては「高い」というイメージがあるようだ。それでは、日本でカステラを始めて伝えた人は、日本でソースの材料が近くに見あたらず、省いたのだろうか。
オリジナルって?
その場にあるもので作るといえば、新鮮な魚が少ない北ヨーロッパ内陸で過ごす私は、「日本料理」というものを作ることを頼まれる機会に会えば、スモークサーモンや、アボカドやら、ツナマヨを巻物の中に使う。参加する人数が多ければ、巻き鮨を自分で作るのは面倒なので、所謂現代的な「手巻き」にしてしまい、其々が好きなものを好きなだけ巻いて食べるシステムでセッティングすることもある。
そして、こんないいかげんな日本人が作って出した料理でも、ヨーロッパ人には「伝統的オリジナル日本料理」として恭しく受け入れられる。こういう環境に合わせ、或いは作るほうの勝手な都合によって、文化というものは常に変化して伝達されていくのだ。
さて、人は自身の文化の伝統を、ある程度モダンに独断でアレンジすることは厭わないにもかかわらず、その「オリジナル」のアレンジに、ある程度の境界をも作りたがるものだ。例えば西欧人が巻物に「にんじんスティック」を入れて、醤油をフランス料理のソースよろしく、ジャブジャブかけているのを見るのは、どうしても受け入れられなかったり、食後にカップが見あたらなかったからと、木のお椀にコーヒーを入れて飲まれたりしたらもう最後、日本人としてのアイデンティティーが壊されるとばかりに大騒ぎする。
ここまでがオリジナルですよ、と境界線を引くときに、人は突如として「我々の文化ではこうだから。」と自文化を背負って見せたりするのだが、その境界作りは、あくまで自分勝手な基準設定でしかない。自文化に対する「オリジナル」性、つまり自分自身のオリジナリティーが否定されないように基準を設けないと、人は不安になってしまうからだ。しかし、カステラがその形を持って初めてカステラとしてありえたように、元来文化のオリジナリティーも、その瞬間に生まれたものに過ぎないのではないだろうか。
|