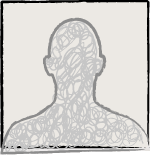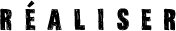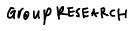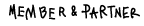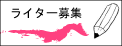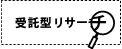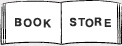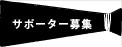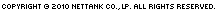|
日本ではなかなか触れる機会の少ないドイツ映画。 でも、ドイツにはハリウッドに次ぐ規模の大スタジオもあったりして、映画産業は実はとっても元気。 私の住んでいるベルリンでは、個性的なミニシアターもまだまだがんばっていて、良質なインディー作品もきちんと上映されています。 このコーナーでは、そんなドイツ映画の「いま」を、私なりにお伝えしてゆきたいと思っています。
第一話
『泣く駱駝の物語』 Die Geschichte vom weinenden Kamel
~ 対話としてのドキュメンタリー ~
駱駝の涙?!
ポスターの中で白い幼毛につつまれた駱駝の子供が、なんともいえない表情を浮かべている。 かなりひん曲がった口元は、ほおばった草を食んでいるようにも、言葉にならない何かを伝えたがっているようにも見える。 背後には母親と思われる成熟した駱駝がもう一頭、広々とした空の青さと淡い草の緑を帯びた砂色の中に静かに佇んでいる――。
動物好きならずとも、一体何の映画なのかと思わず立ち止まってしまいたくなるような魅力的なポスターだ。 モンゴルを舞台にしたこの映画、タイトルは直訳すると「泣く駱駝の物語」。 泣くって言ったってやっぱり動物なんだから、どうせ比喩だと思うでしょう? ところが比喩ではないのだ。 この映画の中で、駱駝は本当に涙を流す。 これは、まさしくその駱駝の涙の瞬間を追ってつくられたドキュメンタリー映画なのである。
母駱駝に拒絶された赤ちゃん駱駝
モンゴルの南、ゴビ砂漠に放牧生活を送るある一家のもとで、一頭の駱駝の赤ん坊が生まれようとしている。 しかし、赤ん坊が大きすぎるのか、出産は長引き、母駱駝はそれこそ身をよじって苦しんでいる。 ようやく生まれた赤ん坊は、珍しいことに、真っ白な体毛で覆われた、とても美しい駱駝だった。
まだ目も開かないこの大柄の赤ん坊は、乳を求めて母駱駝に身を摺り寄せる。 ところが、母駱駝の方は、なぜか子駱駝を近づけようとしない。 出産の苦しみがよほどひどかったのか、その恨みを苦しみの原因である子駱駝にぶつけているのだろうか。
母親が乳をやろうとしないので、赤ん坊はどんどん弱っていく。 家族は母親をなだめようと、さまざまな手を尽くすが、母駱駝は頑なにこころを閉ざしたままだ。 そこで、一家は古くから伝わる儀式によって問題の解決を図ることにする。 町から楽師の先生を呼び、音楽を奏でてもらい、母駱駝に涙を流させ、息子と仲直りさせるる、というのがその儀式。 果たしてうまくいくのだろうか?
世界的評価を受けた学生映画
プロデューサー、トビアス・N・ジーベルトは、ハイゼンベルクやヴェンダースなどを輩出したドイツ屈指の映画学校、ミュンヘン映画大学(HFF)の現役の学生。 監督は、やはりHFF出身のビアムバズレン・ダヴァと、イタリア出身のルイジ・ファロルニ。 ドイツ(ジーベルト)、モンゴル(ダヴァ)、イタリア(ファロルニ)と、三人三様の国籍をもつ学生スタッフによって作られたこの映画、地元ミュンヘンの映画祭で公開されるや、たちまち評判を呼び、各映画祭で賞を総なめ、いまやオスカー外国語映画賞にノミネートされるほどの成功を収めた。
とはいえ、映画作りそのものは、下世話な賞狙いとは程遠いこまやかなもの。 撮影は、モンゴル出身のダヴァの、自らのルート、放牧民の生活そのものに対する強い関心に端を発している。
モンゴル、都会と草原―二つの世界
自身は放牧民としてではなく、若い頃に町に出た両親のもとで近代的な教育を受けたダヴァは、子供の頃、町の映画館で放映されていたある映画によってこの儀式を知ったという。 祖父母の時代には日常のものであった音楽による儀式は、近代化が進み、放牧生活を捨て町へ出るものが増えるに連れて、次第に伝説の色彩を濃くしていったのだろう。 それを実際に目で見、耳で聞き、さらに映像として収めたいという彼女の強い願いに導かれて、映画は静かに、しかし力づよく、ノマドたちの暮らしを綴ってゆく。
放牧生活を捨てて町に出た両親のもとでモンゴル人として生まれ育ち、ドイツの教育機関で映画作りを学んだ彼女は、いわば二重の意味で、二つの世界のあいだに立っていると言える。 時に対立し、時に融和しながらストーリーを織り上げているこの二つの世界は、ダヴァ本人におけるそれに留まらず、ヨーロッパとアジア、伝統と進歩、自然と人口など、近代の確立以来さまざまな形で変奏されてきた二項対立へと姿を変え、作品のそこここに書き込まれている。


]『壁に向かって』 Gegen die Wand(独 2004年)
『兵士と女王』 Der Krieger und die Kaiserin
『演劇中毒』 Die Spielwutigen
|