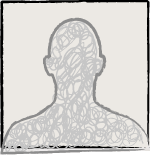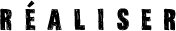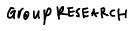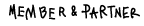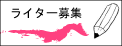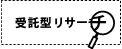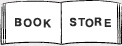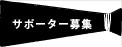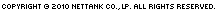|
日本ではなかなか触れる機会の少ないドイツ映画。 でも、ドイツにはハリウッドに次ぐ規模の大スタジオもあったりして、映画産業は実はとっても元気。 私の住んでいるベルリンでは、個性的なミニシアターもまだまだがんばっていて、良質なインディー作品もきちんと上映されています。 このコーナーでは、そんなドイツ映画の「いま」を、私なりにお伝えしてゆきたいと思っています。
第四話
『壁に向かって』 Gegen die Wand(独 2004年)
――心の中の国境――
奇妙な出会い
昨日の夜半、酔っ払った挙句またしても人生に絶望し、車ごと壁に追突する、という乱暴な自殺を試みるが、結局は鞭打ち症になってしまっただけのアル中男、チャヒト。通院中の病院の待合室でふと眼差しを上げると、待ち構えていたように彼の視線を捉える別の視線がある。無垢でありながらどこか挑発的なその瞳。やはりトルコ系の美しいその娘の両手首には、大袈裟なほど包帯が巻きつけられている。ドクターのお説教をやり過ごして、病院を出ようとするチャヒトにかけより、突然声をかけたのが、ほかならぬこの娘、シベルだった。
「あんた、トルコ人でしょ?ねえ、あたしと結婚しない?」
もちろんそんな素っ頓狂な提案は、チャヒトにとってはさして面白くもない冗談でしかない。だが娘のほうはいたってシンケンだ。典型的にトルコ的な厳しい両親の束縛の下、病的に自殺未遂を繰り返してきたシベルにとって、結婚は家族という監獄から逃れるためにひねり出された必死の策なのだ。生きる意味をすっかり失ってすでに久しいチャヒトは結局、娘の迫力におされて、ついに結婚するはめに。
しかし困ったことに、彼との結婚を手っ取り早い単なる逃げ道としか捉えていなかった自由奔放なトルコ娘、ようやくその時が来たというようにあでやかに花開いた若々しいシベルに、チャヒトはすっかり恋してしまうことになる。
今年のベルリン映画祭で、ドイツ映画としては実に18年振りの金の獅子賞受賞となった『壁に向かって』は、ドイツにおけるトルコ人移民の二世たち、という重いテーマとは裏腹に、こんなコミカルな発端から語り起こされる。
とはいえ、偽装結婚から始まった彼らの恋がすんなりと運ぶわけがない。ハンブルクとイスタンブールという二つの港町を舞台に、映画は、トルコ人、ドイツ人、ドイツのトルコ人という3つの視点を錯綜させつつ、チャヒトとシベルの複雑な運命を「ロックに、ダーティーに、けれどリアルに」描いてゆく。
移民の町、ハンブルク
監督ファティ・アキンはハンブルク生まれのトルコ系ドイツ人。その生まれ故郷が映画前半部の舞台となる。ハンブルクはドイツ第一の移民人口を誇る北の大都会。この美しい港町には、南にはエルベ川、中央を内アルスターと外アルスターの二つの人口湖が横たわり、その豊かな水量と、街中に掛けられた大小の橋から、「北のベニス」と呼ばれている。
とはいえ、この映画の中で、「水」は驚くほど不在だ。水のかわりに流れるのは、シベルに出会うまで毎晩チャヒトの胃袋の中に流し込まれていたアルコール、そうでなければ、あるときは怒りから、あるときは持って行き場のない情熱から、むちゃくちゃをやらずにいられない彼ら自身の生温かい血ばかりである。
人口の14%以上(つまり6~7人に一人)を移民が占めるハンブルク、中でもトルコ系は最大人口を占める。一方では大小のショッピングセンター、ドイツ屈指の歓楽街、クラブ文化や、大手の映画プロダクションにメジャーからマイナーまでさまざまな映画館をそなえ、出版社や新聞社も全ドイツの50%以上がここを拠点とするなど、表面的には華やかなトレンド発信地の感が強い。その一方で、汚れ仕事を受け持つ移民やその二世たちがいる。アキン自身、労働者階級の出身だ。
911を「世界の分裂の始まり」と見るアキンがこの映画で試みようとしたのは、一つには善と悪、正義と虚偽、白と黒、闇と光、よそ者と自国人、汚濁と聖性など、さまざまなカテゴライズに示される、使い古されてはいるものの、現実には未だにそのネガティブな効力を失っていない二重化されたモラルを、いまひとたび問い質すことだ。
映画後半部、両親の束縛から解放され自由恋愛を満喫するシベルの愛人の一人を、誤って殺してしまったチャヒトの服役終了を待ちきれずに、本国トルコへと逃れるように出発するシベルとともに、舞台もイスタンブールへと移される。ドイツの人気保養地の一つであるこの街は、ここではしかし期待される華やかな魅力をもって描かれる事はない。


『兵士と女王』 Der Krieger und die Kaiserin
『演劇中毒』 Die Spielwutigen
『泣く駱駝の物語』 Die Geschichte vom weinenden Kamel
|