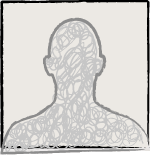|
観光地イスタンブールの明暗
ホテルのベッドメイキングでどうにか糊口をしのいでいたシベルはやがて自暴自棄に陥り、麻薬とアルコールに溺れだす。そんなシベルの周りに、餌をかぎつけた野犬のように暴力の気配が集まってくる。
「善人がほんとに善人なのか、悪人がほんとに悪人なのか、そういうことを僕はこの映画で示したかった。そして、それと同時に、美しいと思われている街が、同時にいかに汚らしくありうるか、それを撮りたかったんだ」と語るアキンの言葉どうり、ここでは意識的に世界的観光地イスタンブールの暗部が強調される。
シベルを説得して同行させたエリート・キャリアウーマンの従妹セルマが経営するホテルに対して、彼女の豪奢だが孤独な生活を一方に据えるなど、あくまでもコントラストにこだわった表現がとられる。そして、いうまでもなく、そのコントラスト自体に含まれる見せ掛けと本質の矛盾をも、映画は見逃すことなく描き出している。
心の中の「壁」
ベルリンの壁が崩壊して早くも15年目が過ぎようとしている。とはいえ、戦後1950年代に開始された「ガストアルバイター(客人労働者)」としての移民受け入れは、70年代以降、すでに定住した移民たちが本国の家族を呼び寄せる、という形でエスカレートし、政府の意向とは反対に、実際には「移民の国」と呼んでもおかしくはないドイツの現状。
そのような状況の中、ハンブルクやベルリンなどの移民集中地域では、ほぼ毎日、右傾化した本国人との葛藤が、事件という形をとって報道されている。
現実の壁はくずれたものの、一人一人の心の中には、別の壁が日々形成されているのだ。そしてその壁は、一国にアイデンティファイすることが実質上(というより実際にははるかにイメージ上)困難なたとえば移民の二世や、外国人同士を両親とする者たちにとっては、自国/他国という単純な二項対立ではおさまりきらない、複雑で流動的な形にならざるをえない。
トルコ系でありながらトルコ語をもはや忘れ掛けているこの作品の主人公、チャヒルにせよ、ハンブルクでもイスタンブールでも心理的には結局「よそ者」のままでいるしかない。それに加えて、世代間の文化的・因習的ギャップも深刻だ。本作の原題『壁に向かって』は、さまざまな意味で、アクチュアルな象徴性を持っている。
異文化問題に注目するベルリン映画祭
イギリスのアイリッシュ問題を扱った一昨年の『血の日曜日』、パキスタンのアフガン移民を素材とした昨年の『イン・ディス・ワールド』など、ベルリン映画祭ではここ数年たてつづけに、異文化間の葛藤を主題とした作品に金の獅子賞が贈られている。この傾向を「政治的」に過ぎると捉える向きもないではない。実際、『壁に向かって』から、トルコXドイツというモチーフを取り去り、単なる情熱的な悲恋映画としてみたならば、今回の受賞には首をひねらざるを得ない部分もないとは言えない。
しかし、トルコ人のガールフレンドにかつて実際に偽装結婚をせがまれたという監督自身の実体験から着想されたこの映画は、二つの文化に挟まれたものが否応なく背負わされてしまう葛藤なしにはやはり生まれえなかっただろう。
また、それが例え「政治的」であるとしても、遠くない過去に「ドイツは移民の国ではない!」と声を荒げていたCSU(キリスト教社会同盟)のヴァイゲル(当時蔵相)等に代表される国粋主義的な傾向が一方で日に日に色濃くなる現在のドイツで、このような選択を敢えてしたベルリン映画祭を私は評価したい。それが例え「芸術的」には問題視されうるにせよ。アキンが言う通り、「911以来、平和な秩序が支配する世界を描く事はもはや不可能」なのだから。
* * *
久しぶりに生まれ故郷で・メガホンを取ったアキン、今年8月にはもう一つの故郷イスタンブールでドキュメンタリーの製作を開始している。タイトルは『橋を渡って―イスタンブールのサウンド』。「壁」に続いて、今度は「橋」だ。いうまでもなく「橋」もまた、二つの世界を分かつものでもある。
水の街で撮られながらも、ほとんど水の登場する事のなかった『壁に向かって』。だが、映画の随所に挿入され、トルコの伝統音楽を哀切に奏でるセスラー&セリムオーケストラの背中には、大きく海が開けていた。ディペッシュ・モードやバースデイ・パーティーなど、ヘビーなロックの使い方にも思い入れを感じさせるが、作品の重さを寓話的に軽やかにしてくれる彼らの存在も、この映画の魅力の一つである。
(いとう こう : ドイツ文学/ミュージシャン)
『兵士と女王』 Der Krieger und die Kaiserin
『演劇中毒』 Die Spielwutigen
『泣く駱駝の物語』 Die Geschichte vom weinenden Kamel
|